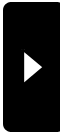2021年06月30日
ひきこもり。
このところ、ひきこもりという言葉に不信感を抱いています。
内閣府のひきこもりの定義は
「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、
非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、
原則的には6ヵ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態
(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念」です。
(引用元「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
学校、アルバイトや仕事といった外との交流を避け、
原則的には6ヶ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態です。
他者と直接的な交流を持たない外出(買い物・ドライブ)は可能なこともあります。
ひきこもりの原因は、ストレスや環境の変化によるもの、
精神的な疾患によるものなど様々で、1つに特定できない場合が多くあります。
ひきこもり、不登校、問題行動等の相談窓口の活動を始めて
約3年が経過しました。
この3年間で相談にこられた家族の方々のお話をお聞きしていますと、
「これってひきこもりになるのかなぁ?
ひきこもりっていうの、おかしくないのかなぁ?」と
思うことが度々です。
不登校も同様です。
文科省の不登校の定義は
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上
欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。
例えばですが、内科的な疾患や大怪我が原因で
治療中、療養中だったりして、それが6ヶ月以上の
月日を要したとしても、
世間ではひきこもりとは言わないのではないでしょうか?
「我が子がひきこもっています。どうすれば・・・。」と
えこーに来られる相談者さんのお話を伺ってますと、
うつや強迫性障害、その他の症状で動けない、出られない。
だから休養し、療養しているのに。
精神的にも身体的にも、しんどくてしんどくて、
どうしたらいいのか分からないから
苦しんでいるのに。
生まれてからずっとひきこもっているのではなく、
一生懸命頑張ってきて、
しんどくてもまだまだ頑張ってきて、
無理をしすぎて、疲れきって、傷ついて、
動けなくなり、活動できなくなった。
どうしてかな?
内科的や外科的に治療中、療養中と、
どうして同じじゃないのかな?
精神疾患や発達障害の診断を受けたら、
学校に行けなくても不登校と言われずにすむのかな。
ひきこもり、不登校ではなく、
療養中なので外出できませんって
世間に認めてもらえるのか?
なーんか、腑に落ちないなー。
なーんか、おかしいよなー。
なーんか、違うよなー。
っと腑に落ちないわけで、
不信感が渦巻いています。
どなたかご意見をいただけると
嬉しいです。
えこステの予定、ホームページ更新しました。
ホームページのアドレスです。
詳しくは下記をポチっとご覧ください
http://ekou-ekochan.sakura.ne.jp
内閣府のひきこもりの定義は
「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、
非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、
原則的には6ヵ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態
(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念」です。
(引用元「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
学校、アルバイトや仕事といった外との交流を避け、
原則的には6ヶ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態です。
他者と直接的な交流を持たない外出(買い物・ドライブ)は可能なこともあります。
ひきこもりの原因は、ストレスや環境の変化によるもの、
精神的な疾患によるものなど様々で、1つに特定できない場合が多くあります。
ひきこもり、不登校、問題行動等の相談窓口の活動を始めて
約3年が経過しました。
この3年間で相談にこられた家族の方々のお話をお聞きしていますと、
「これってひきこもりになるのかなぁ?
ひきこもりっていうの、おかしくないのかなぁ?」と
思うことが度々です。
不登校も同様です。
文科省の不登校の定義は
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上
欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。
例えばですが、内科的な疾患や大怪我が原因で
治療中、療養中だったりして、それが6ヶ月以上の
月日を要したとしても、
世間ではひきこもりとは言わないのではないでしょうか?
「我が子がひきこもっています。どうすれば・・・。」と
えこーに来られる相談者さんのお話を伺ってますと、
うつや強迫性障害、その他の症状で動けない、出られない。
だから休養し、療養しているのに。
精神的にも身体的にも、しんどくてしんどくて、
どうしたらいいのか分からないから
苦しんでいるのに。
生まれてからずっとひきこもっているのではなく、
一生懸命頑張ってきて、
しんどくてもまだまだ頑張ってきて、
無理をしすぎて、疲れきって、傷ついて、
動けなくなり、活動できなくなった。
どうしてかな?
内科的や外科的に治療中、療養中と、
どうして同じじゃないのかな?
精神疾患や発達障害の診断を受けたら、
学校に行けなくても不登校と言われずにすむのかな。
ひきこもり、不登校ではなく、
療養中なので外出できませんって
世間に認めてもらえるのか?
なーんか、腑に落ちないなー。
なーんか、おかしいよなー。
なーんか、違うよなー。
っと腑に落ちないわけで、
不信感が渦巻いています。

どなたかご意見をいただけると
嬉しいです。

えこステの予定、ホームページ更新しました。
ホームページのアドレスです。
詳しくは下記をポチっとご覧ください

http://ekou-ekochan.sakura.ne.jp
Posted by いとう茂 at
21:53
│Comments(0)
2021年06月27日
今日のえこステ・発達障害勉強会①(*^▽^*)
今日は13回目のひきこもり、不登校家族の会
えこちゃんステーションの月例会でした。
今日は発達障害勉強会①なるものを開催しました。
勉強会と言っても、難しい勉強会ではなく、
「大人の発達障害」の基礎知識を知る?読む?
ん-ー、
知る?読む?
読む。。。かな。
「生きにくさ」の説明などが主となりました。
読めば読むほど、
我が子が「生きにくさ」と戦ってきたこと、
「生きづらさ」を頑張ってきたこと、
それがどんなに大変だったか、など、
いろんなことを個々に考える時間になっていたのではないか、
と思います。
今日から新しいメンバーが2名、
えこステに入会して下さいました。
初めて参加下さった日が勉強会の日となりましたので、
緊張されていたかもしれません。
近況報告の時に、ご自分のお家の状況などをお話し下さいました。
えこーでできる事、えこステのメンバー同士でできる事が
あると思います。
何が出来るか、何を求めるか、人それぞれだと思いますが、
それぞれであっても、えこステの例会や、
えこステのメンバーさん達と顔を合わせふれあうことが
心の拠りどころとなり、
ご家族の癒やしやエネルギー補給の場所となりますように
勉強会も無事に終わりましたので、
今晩から広報紙の記事作成に取り掛からないと。
やっぱり明日からにしようかな・・・・。
えこステの予定、ホームページ更新しました。
いつも更新の作業をしてくれている Iさん、
ありがとうございます
ホームページのアドレスです。
詳しくは下記をポチっとご覧ください
http://ekou-ekochan.sakura.ne.jp
えこちゃんステーションの月例会でした。
今日は発達障害勉強会①なるものを開催しました。
勉強会と言っても、難しい勉強会ではなく、
「大人の発達障害」の基礎知識を知る?読む?
ん-ー、
知る?読む?
読む。。。かな。
「生きにくさ」の説明などが主となりました。
読めば読むほど、
我が子が「生きにくさ」と戦ってきたこと、
「生きづらさ」を頑張ってきたこと、
それがどんなに大変だったか、など、
いろんなことを個々に考える時間になっていたのではないか、
と思います。
今日から新しいメンバーが2名、
えこステに入会して下さいました。
初めて参加下さった日が勉強会の日となりましたので、
緊張されていたかもしれません。
近況報告の時に、ご自分のお家の状況などをお話し下さいました。
えこーでできる事、えこステのメンバー同士でできる事が
あると思います。
何が出来るか、何を求めるか、人それぞれだと思いますが、
それぞれであっても、えこステの例会や、
えこステのメンバーさん達と顔を合わせふれあうことが
心の拠りどころとなり、
ご家族の癒やしやエネルギー補給の場所となりますように

勉強会も無事に終わりましたので、
今晩から広報紙の記事作成に取り掛からないと。
やっぱり明日からにしようかな・・・・。

えこステの予定、ホームページ更新しました。
いつも更新の作業をしてくれている Iさん、
ありがとうございます

ホームページのアドレスです。
詳しくは下記をポチっとご覧ください

http://ekou-ekochan.sakura.ne.jp
Posted by いとう茂 at
21:01
│Comments(0)
2021年06月26日
明日はえこステの日です
明日はひきこもり、不登校家族の会
えこちゃんステーションの定例会です。
第2回ひきこもり講座も無事に終わり、
今月から、4回(6月、7月、8月、9月)
発達障害の勉強会をします。
発達障害と一言で説明することの難しさを思いながら、
参考になる本を探したり、
いくつも受けてきた発達障害に関する研修の資料を
じっくり読んでおさらいをしています。
十人十色、ひとりひとり違うように、
発達障害と診断された人の全員が
同じ状態とは言えません。
そう考えると、説明の難しさに頭をポリポリと・・・。
「どんな文献を引用するのが分かりやすいんだろう?」
ひきこもり、不登校の当事者の一番の理解者は家族であり、
一番の支援者も家族です。
抱えている生きづらさを理解することは、
支援することへと、つながるように思います。
「どうして出来ないのか、どうしてこんな状況になってしまったのか?」
それが少しでも分かれば、
「辛く苦しかったことを言うことも出来ず、こんなにも頑張っていたのか。」と
理解することになるのではないかと思います。
少しでも理解することができれば、
当事者が悪いのではなく、
状況に見合った環境ではなかったから、とか
歯車がかみ合っていなかったから、とか
いろいろなことが見えてくるかもしれません。
いろいろなことが見えてきた時、
「本当にこんな辛い状況の中を精一杯、限界を超えて
頑張りすぎてきていたから、
気力も元気もなくなって、外へ出る事、
誰かと接することが出来なくなってしまったのか。」と気付くと共に、
一人で頑張ってきた我が子に愛しさを感じるのではないかと
思います。
理解すること、支えていくこと、
親もやり方が分からなかったから
やり方が違っただけで、
子どもがひきこもったは親のせいでもありません。
これもまた一言で説明することが難しいのですが、
明日から始める発達障害勉強会で、
個々に何かを感じる、学べる時間になることを願っています。
えこちゃんステーションの定例会です。
第2回ひきこもり講座も無事に終わり、
今月から、4回(6月、7月、8月、9月)
発達障害の勉強会をします。
発達障害と一言で説明することの難しさを思いながら、
参考になる本を探したり、
いくつも受けてきた発達障害に関する研修の資料を
じっくり読んでおさらいをしています。
十人十色、ひとりひとり違うように、
発達障害と診断された人の全員が
同じ状態とは言えません。
そう考えると、説明の難しさに頭をポリポリと・・・。
「どんな文献を引用するのが分かりやすいんだろう?」
ひきこもり、不登校の当事者の一番の理解者は家族であり、
一番の支援者も家族です。
抱えている生きづらさを理解することは、
支援することへと、つながるように思います。
「どうして出来ないのか、どうしてこんな状況になってしまったのか?」
それが少しでも分かれば、
「辛く苦しかったことを言うことも出来ず、こんなにも頑張っていたのか。」と
理解することになるのではないかと思います。
少しでも理解することができれば、
当事者が悪いのではなく、
状況に見合った環境ではなかったから、とか
歯車がかみ合っていなかったから、とか
いろいろなことが見えてくるかもしれません。
いろいろなことが見えてきた時、
「本当にこんな辛い状況の中を精一杯、限界を超えて
頑張りすぎてきていたから、
気力も元気もなくなって、外へ出る事、
誰かと接することが出来なくなってしまったのか。」と気付くと共に、
一人で頑張ってきた我が子に愛しさを感じるのではないかと
思います。
理解すること、支えていくこと、
親もやり方が分からなかったから
やり方が違っただけで、
子どもがひきこもったは親のせいでもありません。
これもまた一言で説明することが難しいのですが、
明日から始める発達障害勉強会で、
個々に何かを感じる、学べる時間になることを願っています。

Posted by いとう茂 at
20:17
│Comments(0)
2021年06月22日
こら!こら!! やめなさーい。
今日は6月22日。
6月も終わりに近づいています。
6月中にえこーの広報紙「ハートレター第5号」を
仕上げて発行しよう!と予定をしていましたが・・
第5号の記事は何にしよう?とスタッフ会議を開きました。
・令和2年度の決算報告
・令和2年度の事業報告
・えこステだより
・助成金事業の報告
・第2回ひきこもり講座
以後、「 」は実際にあった会話、
( )は心の声です。
「この5つは絶対に載せんとあかんよなぁ。」
「新聞記事に載ったことも、入れる方がいいのかなぁ。」
「えこステも、令和2年度の振り返りがいるよなぁ。」
(ちょっと待ってー。すごい量の記事やわ。
これっていつものA3の大きさ1枚に載せられるの? )
)
そして、どちらともなく、ほとんど同時に、
「広報紙、今回は枚数を・・・・。」
(こら!やめなさい!!
この先を言うたら、
いつもの2倍の記事を載せることになるんやで!
いつもの広報紙でも四苦八苦して
作っているのに、
倍になったら八苦十六苦になるで
用事が増えるから、やめなさい!!)
「枚数を増やさないと載せきらへんよな。」
(うわー!
今どっちが言うたんやろ?
どっちが言うたか分からんぐらい、
同時に言うてるやん
やめなさいって言うてるのに、
なんでやねーん。 )
)
そんな経緯があり、
ハートレター第5号は、A3用紙2枚で発行することになりました。
ところが、6月27日(日)のえこステで
発達障害の勉強会を始めます。
4か月に渡り、全4回で
発達障害の勉強会を開催します。
そのための資料作りを先にやらないと・・・。
6月28日(月)は会議が入っているし、
毎水・日曜日は面談で詰まってるし、
広報紙作成に取り掛かる時間あるのかなぁ。
だからあれほど、やめなさい!って言うたでしょうが!!
6月も終わりに近づいています。
6月中にえこーの広報紙「ハートレター第5号」を
仕上げて発行しよう!と予定をしていましたが・・

第5号の記事は何にしよう?とスタッフ会議を開きました。
・令和2年度の決算報告
・令和2年度の事業報告
・えこステだより
・助成金事業の報告
・第2回ひきこもり講座
以後、「 」は実際にあった会話、
( )は心の声です。

「この5つは絶対に載せんとあかんよなぁ。」
「新聞記事に載ったことも、入れる方がいいのかなぁ。」
「えこステも、令和2年度の振り返りがいるよなぁ。」
(ちょっと待ってー。すごい量の記事やわ。
これっていつものA3の大きさ1枚に載せられるの?
 )
)そして、どちらともなく、ほとんど同時に、
「広報紙、今回は枚数を・・・・。」
(こら!やめなさい!!
この先を言うたら、
いつもの2倍の記事を載せることになるんやで!
いつもの広報紙でも四苦八苦して
作っているのに、
倍になったら八苦十六苦になるで

用事が増えるから、やめなさい!!)
「枚数を増やさないと載せきらへんよな。」
(うわー!
今どっちが言うたんやろ?
どっちが言うたか分からんぐらい、
同時に言うてるやん

やめなさいって言うてるのに、
なんでやねーん。
 )
)そんな経緯があり、
ハートレター第5号は、A3用紙2枚で発行することになりました。
ところが、6月27日(日)のえこステで
発達障害の勉強会を始めます。
4か月に渡り、全4回で
発達障害の勉強会を開催します。
そのための資料作りを先にやらないと・・・。

6月28日(月)は会議が入っているし、
毎水・日曜日は面談で詰まってるし、
広報紙作成に取り掛かる時間あるのかなぁ。
だからあれほど、やめなさい!って言うたでしょうが!!

Posted by いとう茂 at
21:39
│Comments(0)
2021年06月19日
第2回ひきこもり講座のご報告⑦
ひきこもり講座のご報告⑥の続きです。
障害年金について、いつもネックになってくるのは初診日です。
初診日というのは、障害の原因となった病気とか怪我について、
初めて医師の診療を受けた日を初診日と言います。
初診日がいつだったのか、どこの病院だったのかということが
必要になってきます。なかなか難しいですね。
自分で確認することはとても難しい部分だと思います。
後は、申請にかかる期間、初診日の前日において、
初診日がある月の2か月前まで、
保険料の納付要件を満たしていないといけない。
よく分からないですよね、難しい。
要は、無職の方、仕事をしていない方、
扶養は入っているけれど、年金は払っていない、
ほったらかしという方がもし、いらっしゃたら、
とりあえず減免手続きはしておいた方がいいと思います。
何もしていないと、ただ払っていないだけになっちゃうので、
そうすると、後から障害年金が必要となった時に
受けられなくなってしまいます。
未納だけは避けていきたいですね。
未納と免除はまた違いますので、基本的に免除できるものは、
免除申請をしておくことをお勧めします。
じゃないと、未納の状態が続いてしまうと、
ご両親が亡くなった後、ご本人さんが残っても、
老齢年金も受け取ってしまえなくなります。
年金については、障害年金ガイドというものを
年金事務所でもらうことができます。
続いて、どんな時にどんな社会資源があるの?
についての続きです。
生活、生活品に関することについては、
いろんな相談できる窓口がありますが、
大津の場合は、自立相談支援機関というものがあります。
大津の場合は、大津市の生活福祉課や大津市社会福祉協議会が
主な自立相談支援機関となっています。
後はNPO大津夜回りの会というところも
自立相談支援機関のひとつとなっています。
今で言うと、コロナによる失業や減収による特例貸付なんかは、
大津市社会福祉協議会が窓口になっています。
他の市町でも社会福祉協議会が窓口となって、
特例の貸付の申請を出来ることになっています。
それから生活保護についてですが、
市町の担当課、大津で言えば生活福祉課になります。
借金整理や自己破産については、
司法書士や弁護士の相談になるんですけど、
ここも自分では、なかなか難しいという場合は、
自立相談支援機関への相談の中で、
社会福祉協議会にも顧問の司法書士、弁護士はおりますので、
そこの相談に繋ぐ場合があります。
実際に債務等の整理の手続きを進める場合には、
そこで改めて司法書士や
弁護士との契約に基づいて費用は発生しますが、
相談については無料です。
また、行政相談なんかでも、
法律相談に関することもありますし、
まずはご相談いただけると少し動きが
出せるかなというふうに思います。
ある程度、社会資源のことを知っておくと少し安心できますよね。
それでも社会資源を利用するのは本人です。
本人から困ったことを素直に困ったと
言ってもらえる関係性が出来ることが一番いいなと思います。
当たり前かもしれませんが、難しいですね。
特にご家族同士、親子関係は難しいと思います。
なので、ご本人と向き合う時、どうしても苛立って
上手いこと自分の思いがぶつけられへん等
なんとなく聞く側に回れない、
自分にそんな気持ちの余裕がないという場合は、
まず自分がぶつけたい思いは、第3者の相談員か窓口の方に
ぶつけていただいたらと思います。
そこで吐いていただいて、家に帰って、
ひきこもり当事者と向き合う時には、
自分の気持ちに余裕を持ってもらって、
基本的には相手の思いや変化を汲み取るような姿勢でいけると
いいなと願っています。
しんどいという思いは家の中で吐き出すのではなく、
外で吐き出せるようにという意味で
相談に繋がってもらいたいと思います。
以上で第2回ひきこもり講座のご報告終了です。
今回の講座開催で新しい相談者さん2名とつながりました。
家族の会えこステにもご参加下さいます。
このご縁を大切に、寄り添っていけるよう、
えこーのスタッフ、がんばります!!
障害年金について、いつもネックになってくるのは初診日です。
初診日というのは、障害の原因となった病気とか怪我について、
初めて医師の診療を受けた日を初診日と言います。
初診日がいつだったのか、どこの病院だったのかということが
必要になってきます。なかなか難しいですね。
自分で確認することはとても難しい部分だと思います。
後は、申請にかかる期間、初診日の前日において、
初診日がある月の2か月前まで、
保険料の納付要件を満たしていないといけない。
よく分からないですよね、難しい。
要は、無職の方、仕事をしていない方、
扶養は入っているけれど、年金は払っていない、
ほったらかしという方がもし、いらっしゃたら、
とりあえず減免手続きはしておいた方がいいと思います。
何もしていないと、ただ払っていないだけになっちゃうので、
そうすると、後から障害年金が必要となった時に
受けられなくなってしまいます。
未納だけは避けていきたいですね。
未納と免除はまた違いますので、基本的に免除できるものは、
免除申請をしておくことをお勧めします。
じゃないと、未納の状態が続いてしまうと、
ご両親が亡くなった後、ご本人さんが残っても、
老齢年金も受け取ってしまえなくなります。
年金については、障害年金ガイドというものを
年金事務所でもらうことができます。
続いて、どんな時にどんな社会資源があるの?
についての続きです。
生活、生活品に関することについては、
いろんな相談できる窓口がありますが、
大津の場合は、自立相談支援機関というものがあります。
大津の場合は、大津市の生活福祉課や大津市社会福祉協議会が
主な自立相談支援機関となっています。
後はNPO大津夜回りの会というところも
自立相談支援機関のひとつとなっています。
今で言うと、コロナによる失業や減収による特例貸付なんかは、
大津市社会福祉協議会が窓口になっています。
他の市町でも社会福祉協議会が窓口となって、
特例の貸付の申請を出来ることになっています。
それから生活保護についてですが、
市町の担当課、大津で言えば生活福祉課になります。
借金整理や自己破産については、
司法書士や弁護士の相談になるんですけど、
ここも自分では、なかなか難しいという場合は、
自立相談支援機関への相談の中で、
社会福祉協議会にも顧問の司法書士、弁護士はおりますので、
そこの相談に繋ぐ場合があります。
実際に債務等の整理の手続きを進める場合には、
そこで改めて司法書士や
弁護士との契約に基づいて費用は発生しますが、
相談については無料です。
また、行政相談なんかでも、
法律相談に関することもありますし、
まずはご相談いただけると少し動きが
出せるかなというふうに思います。
ある程度、社会資源のことを知っておくと少し安心できますよね。
それでも社会資源を利用するのは本人です。
本人から困ったことを素直に困ったと
言ってもらえる関係性が出来ることが一番いいなと思います。
当たり前かもしれませんが、難しいですね。
特にご家族同士、親子関係は難しいと思います。
なので、ご本人と向き合う時、どうしても苛立って
上手いこと自分の思いがぶつけられへん等
なんとなく聞く側に回れない、
自分にそんな気持ちの余裕がないという場合は、
まず自分がぶつけたい思いは、第3者の相談員か窓口の方に
ぶつけていただいたらと思います。
そこで吐いていただいて、家に帰って、
ひきこもり当事者と向き合う時には、
自分の気持ちに余裕を持ってもらって、
基本的には相手の思いや変化を汲み取るような姿勢でいけると
いいなと願っています。
しんどいという思いは家の中で吐き出すのではなく、
外で吐き出せるようにという意味で
相談に繋がってもらいたいと思います。
以上で第2回ひきこもり講座のご報告終了です。
今回の講座開催で新しい相談者さん2名とつながりました。
家族の会えこステにもご参加下さいます。
このご縁を大切に、寄り添っていけるよう、
えこーのスタッフ、がんばります!!
Posted by いとう茂 at
20:38
│Comments(0)
2021年06月15日
第2回ひきこもり講座のご報告⑥
ひきこもり講座のご報告⑤の続きです。
では、どんな時にどんな社会資源があるのでしょうか?
ひきこもり支援の中でよく出てくるのが、
精神科、心療内科の受診になります。
ここで出てくるのが
【自立支援医療(精神通院医療)】といわれるもので、
自己負担が原則1割になります。
市役所経由で県の方で発行するのが、
【自立支援医療受給者証】。
手続きは各市町の障害福祉担当課になります。
次に【精神障害者保健福祉手帳】。
手帳があると何がいいか?
メリットは、障害福祉サービスを利用する時に、
スムーズに利用することができます。
A型、B型、グループホームにつながる時に、
手帳を持っていることが条件になる場合が出てきます。
この資源を上手く使うにはどうするか?
相談機関でもいいのですが、受診ということであれば、
受診して受付の方に聞いていただければいいかなと
思います。
受診した時に、
「あれ持ってるか?これ持ってるか?」と聞かれる場合が
あると思います。
相談機関に繋がっている状態で医療受診が必要となった場合は、
相談の段階で、そういった手続きをする場合も
出てくると思います。
では次、【障害年金】についてです。
申請窓口は市区町村役場、または
お近くの年金事務所なのですが、
年金事務所が一番確実かなと思います。
障害年金の申請は結構大変です。
相談を聞いてやりかけたけど、
ちょっと私ひとりでは進められないと思ったので、
社会保険労務士の方にお願いしました。
より専門的にサポートしてもらえるのが社会保険労務士ですが、
お金はかかりますが、
動いてもらうためにお金がかかるのではなく、
障害年金を申請して、
申請が通った時に成功報酬として、
費用がかかる場合が多いです。
一回、相談だけでも、してみる価値はあります。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです。
では、どんな時にどんな社会資源があるのでしょうか?
ひきこもり支援の中でよく出てくるのが、
精神科、心療内科の受診になります。
ここで出てくるのが
【自立支援医療(精神通院医療)】といわれるもので、
自己負担が原則1割になります。
市役所経由で県の方で発行するのが、
【自立支援医療受給者証】。
手続きは各市町の障害福祉担当課になります。
次に【精神障害者保健福祉手帳】。
手帳があると何がいいか?
メリットは、障害福祉サービスを利用する時に、
スムーズに利用することができます。
A型、B型、グループホームにつながる時に、
手帳を持っていることが条件になる場合が出てきます。
この資源を上手く使うにはどうするか?
相談機関でもいいのですが、受診ということであれば、
受診して受付の方に聞いていただければいいかなと
思います。
受診した時に、
「あれ持ってるか?これ持ってるか?」と聞かれる場合が
あると思います。
相談機関に繋がっている状態で医療受診が必要となった場合は、
相談の段階で、そういった手続きをする場合も
出てくると思います。
では次、【障害年金】についてです。
申請窓口は市区町村役場、または
お近くの年金事務所なのですが、
年金事務所が一番確実かなと思います。
障害年金の申請は結構大変です。
相談を聞いてやりかけたけど、
ちょっと私ひとりでは進められないと思ったので、
社会保険労務士の方にお願いしました。
より専門的にサポートしてもらえるのが社会保険労務士ですが、
お金はかかりますが、
動いてもらうためにお金がかかるのではなく、
障害年金を申請して、
申請が通った時に成功報酬として、
費用がかかる場合が多いです。
一回、相談だけでも、してみる価値はあります。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです。

Posted by いとう茂 at
22:40
│Comments(0)
2021年06月14日
第2回ひきこもり講座のご報告⑤
ひきこもり講座のご報告④の続きです。
社会資源探す時に非常に苦労するんですよね。
何が使えるか分からない。
同じようなしんどさを抱えている人と出会った時に、
「あなた、それを使ってるんだ。私も使えるかな?」
ってことで、その資源に繋がるということが非常に多い。
私も資料を作る時に大津市のホームページの
福祉のところだけを見たのですが、
知らない制度とかが、たくさんあるんですよ。
相談員をするうえで、言葉とか知識とか、
ある程度は覚えているつもりではあるんですけど、
それでも全然足りない。
浅く広く相談できる相談員と、専門的な相談員がいますので、
そこを上手く使い分けていく必要があるかなと思います。
一旦、分からない場合は、浅く広くの相談員に相談したうえで、
より専門的な相談員に繋がっていくようにして頂いたらいいと思います。
もうひとつ追加で、例えば相談機関ひとつ、
えこーに相談してるという場合に、
じゃあ、社協に相談してはいけないと思っておられますか?
相談機関はいくつ使っていただいても構いません。
あそこに相談したけど、ダメやったからこっちというふうに、
どれかひとつしか選べないというものでは決してないんです。
相談機関それぞれ得意分野と苦手分野があります。
いわゆる情報量が多い分野と少ない分野がありますので、
行った相談機関が自分の欲しかった答えと違ったとしても、
適した機関に繋げてもらえますので、
どうしたらいいか分からない時は、どこかへ行って、
まず喋ってみる、繋がってみるということがいいかなと思います。
社会資源と繋がるにはどうしたらいいか?
・各種相談窓口を利用する。
・直接自分で手続き等を行う。
・誰か第三者に依頼して動いてもらう。
とりあえず、匿名で相談することが可能です。
相談窓口へ行った時、名前、住所を受付票に
書いてもらっていますが、
書きたくない!といった方は、書かなくても大丈夫です。
心配なのは、匿名での相談は1回キリで切れてしまいます。
継続的な相談や、他の機関にきちんと繋いでほしいという場合は、
基本的な受付をお願いしたいと思っています。
社会資源を利用するには、何に困っているかを
整理しなければなりません。
これがすごく難しくて、ひとりではなかなか整理できません。
なので、困った時には相談窓口に
相談いただいた方がいいと思います。
社会資源を活用するには、ひとりでは、しんどい、
大変ですので、その時のために相談員がいます。
では、どんな時にどんな社会資源があるのでしょうか?
本日はここまでで、
続きは次回のブログです。
ひきこもり講座の報告はまだまだ続きます!
社会資源探す時に非常に苦労するんですよね。
何が使えるか分からない。
同じようなしんどさを抱えている人と出会った時に、
「あなた、それを使ってるんだ。私も使えるかな?」
ってことで、その資源に繋がるということが非常に多い。
私も資料を作る時に大津市のホームページの
福祉のところだけを見たのですが、
知らない制度とかが、たくさんあるんですよ。
相談員をするうえで、言葉とか知識とか、
ある程度は覚えているつもりではあるんですけど、
それでも全然足りない。
浅く広く相談できる相談員と、専門的な相談員がいますので、
そこを上手く使い分けていく必要があるかなと思います。
一旦、分からない場合は、浅く広くの相談員に相談したうえで、
より専門的な相談員に繋がっていくようにして頂いたらいいと思います。
もうひとつ追加で、例えば相談機関ひとつ、
えこーに相談してるという場合に、
じゃあ、社協に相談してはいけないと思っておられますか?
相談機関はいくつ使っていただいても構いません。
あそこに相談したけど、ダメやったからこっちというふうに、
どれかひとつしか選べないというものでは決してないんです。
相談機関それぞれ得意分野と苦手分野があります。
いわゆる情報量が多い分野と少ない分野がありますので、
行った相談機関が自分の欲しかった答えと違ったとしても、
適した機関に繋げてもらえますので、
どうしたらいいか分からない時は、どこかへ行って、
まず喋ってみる、繋がってみるということがいいかなと思います。
社会資源と繋がるにはどうしたらいいか?
・各種相談窓口を利用する。
・直接自分で手続き等を行う。
・誰か第三者に依頼して動いてもらう。
とりあえず、匿名で相談することが可能です。
相談窓口へ行った時、名前、住所を受付票に
書いてもらっていますが、
書きたくない!といった方は、書かなくても大丈夫です。
心配なのは、匿名での相談は1回キリで切れてしまいます。
継続的な相談や、他の機関にきちんと繋いでほしいという場合は、
基本的な受付をお願いしたいと思っています。
社会資源を利用するには、何に困っているかを
整理しなければなりません。
これがすごく難しくて、ひとりではなかなか整理できません。
なので、困った時には相談窓口に
相談いただいた方がいいと思います。
社会資源を活用するには、ひとりでは、しんどい、
大変ですので、その時のために相談員がいます。
では、どんな時にどんな社会資源があるのでしょうか?
本日はここまでで、
続きは次回のブログです。
ひきこもり講座の報告はまだまだ続きます!

Posted by いとう茂 at
22:28
│Comments(0)
2021年06月13日
第2回ひきこもり講座のご報告④
ひきこもり講座のご報告③の続きです。
社会資源の話に入ります。
社会資源って何でしょうか?というところで、
ここで言う社会資源とは、病院や学校、役所だったりだとか、
人とのつながりとかですね。
多分、社会資源は少ないと思っておられる方が多いと思います。
確かに少ないと言えば少ない。それは実際少ないというよりは、
私が思うには情報が入ってこないんですよ。
自ら集めないと情報は入ってこないし、
申請しないとできない資源が
非常に日本では多いです。
不便ですよね。
自分の状況を1から伝えて相談して説明して申請しないと
受けられない。
そんな制度が非常に多くて、
その部分が多分、今のしんどさに繋がっているんじゃないかなと
資料を作っていて感じていました。
必要な時に必要な情報が手元に残っていない。
その時はいらんと思って回覧とか捨ててしまって、
後から必要になった物ってありませんか?
社会資源に繋がるには、非常に不便だと感じられます。
社会資源(福祉の)とは、
言葉的には福祉向上のための制度や施設のことです。
市民センターや地域のボランティアさんも
社会資源のひとつなんです。
例えば、今でいうとコロナワクチンですかね。
コロナという病気が出なかったら、
コロナワクチンを開発する必要もなかったし、
特効薬の開発も研究者が進めておられると思います。
何かきっかけがあって制度が出来ている。
その制度で補える部分、
補えない部分がまた課題として上がってきて、
新たな制度が出来る。
非常に複雑で多岐に渡っています。
社会資源探す時に非常に苦労するんですよね。
何が使えるか分からない。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです
社会資源の話に入ります。
社会資源って何でしょうか?というところで、
ここで言う社会資源とは、病院や学校、役所だったりだとか、
人とのつながりとかですね。
多分、社会資源は少ないと思っておられる方が多いと思います。
確かに少ないと言えば少ない。それは実際少ないというよりは、
私が思うには情報が入ってこないんですよ。
自ら集めないと情報は入ってこないし、
申請しないとできない資源が
非常に日本では多いです。
不便ですよね。
自分の状況を1から伝えて相談して説明して申請しないと
受けられない。
そんな制度が非常に多くて、
その部分が多分、今のしんどさに繋がっているんじゃないかなと
資料を作っていて感じていました。
必要な時に必要な情報が手元に残っていない。
その時はいらんと思って回覧とか捨ててしまって、
後から必要になった物ってありませんか?
社会資源に繋がるには、非常に不便だと感じられます。
社会資源(福祉の)とは、
言葉的には福祉向上のための制度や施設のことです。
市民センターや地域のボランティアさんも
社会資源のひとつなんです。
例えば、今でいうとコロナワクチンですかね。
コロナという病気が出なかったら、
コロナワクチンを開発する必要もなかったし、
特効薬の開発も研究者が進めておられると思います。
何かきっかけがあって制度が出来ている。
その制度で補える部分、
補えない部分がまた課題として上がってきて、
新たな制度が出来る。
非常に複雑で多岐に渡っています。
社会資源探す時に非常に苦労するんですよね。
何が使えるか分からない。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです

Posted by いとう茂 at
22:12
│Comments(0)
2021年06月11日
第2回ひきこもり講座のご報告③
ひきこもり講座のご報告②の続きです。
ひきこもり状態にある人への配慮ですが、
・ムリさせない。
・特別扱いしない。
・さりげなく支える。
本人は暗いトンネルを歩き通したい。
歩き通したい思いはあるが、どうしたいか分からない。
今は歩き通して出口まで出るエネルギーがない。
親御さんは、どうやったらエネルギーが出るか分からない。
親として何が出来るか分からない。
親御さんは、親のしんどいところを
そのまま相談してほしいです。
ご本人の様子の変化を相談員と一緒に気づいていく。
ここで、元ひきこもり経験者の講演で話されていたことを
お話しします。
「社会的な所属をしていない。
どこにも所属していないことが、
とても恐怖だった。」と。
そして、
「どこにも相談できない。」と話されていました。
もっと詳しく言いますと、
「視野が狭くなっている。」
「どうしたらいいのか。」と悩む。
「相談しても答えは分かっている。」
「相談をして答えを教えてほしいわけではなく、
答えを探す過程、答えを探す途中に、
一緒に答えを考えてくれた人が
今の自分につながっている。」
と話されていました。
相談をする人は答えを欲しいのではなく、
今のしんどい気持ちに共感してほしいのですよ、きっと。
人によって、これが正解ではないんでしょうけど。
答えを知っているけど踏み切れない。
答えに進めない何か理由があると思うと、
「そうか、じゃあ、どうしていこうか。」という返し方になります。
相談員に大切なことは、
正論は役に立たないということです。
正論を言われると、否定されている気持ちになる。
正論は通じません。
正論をぶつける イコール
自分の価値観を押し付けることになる。
そうなると、関係性が悪くなるリスクがあります。
正論を言っても解決しません。
正論をぶつけそうになったら、
自分がイライラし始めているサインです。
正論をぶつけそうになったら、深呼吸をするようにしています。
正論ではなく、
ヒントや選択肢を話しています。
このような思いをもって、相談を受けています。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです
ひきこもり状態にある人への配慮ですが、
・ムリさせない。
・特別扱いしない。
・さりげなく支える。
本人は暗いトンネルを歩き通したい。
歩き通したい思いはあるが、どうしたいか分からない。
今は歩き通して出口まで出るエネルギーがない。
親御さんは、どうやったらエネルギーが出るか分からない。
親として何が出来るか分からない。
親御さんは、親のしんどいところを
そのまま相談してほしいです。
ご本人の様子の変化を相談員と一緒に気づいていく。
ここで、元ひきこもり経験者の講演で話されていたことを
お話しします。
「社会的な所属をしていない。
どこにも所属していないことが、
とても恐怖だった。」と。
そして、
「どこにも相談できない。」と話されていました。
もっと詳しく言いますと、
「視野が狭くなっている。」
「どうしたらいいのか。」と悩む。
「相談しても答えは分かっている。」
「相談をして答えを教えてほしいわけではなく、
答えを探す過程、答えを探す途中に、
一緒に答えを考えてくれた人が
今の自分につながっている。」
と話されていました。
相談をする人は答えを欲しいのではなく、
今のしんどい気持ちに共感してほしいのですよ、きっと。
人によって、これが正解ではないんでしょうけど。
答えを知っているけど踏み切れない。
答えに進めない何か理由があると思うと、
「そうか、じゃあ、どうしていこうか。」という返し方になります。
相談員に大切なことは、
正論は役に立たないということです。
正論を言われると、否定されている気持ちになる。
正論は通じません。
正論をぶつける イコール
自分の価値観を押し付けることになる。
そうなると、関係性が悪くなるリスクがあります。
正論を言っても解決しません。
正論をぶつけそうになったら、
自分がイライラし始めているサインです。
正論をぶつけそうになったら、深呼吸をするようにしています。
正論ではなく、
ヒントや選択肢を話しています。
このような思いをもって、相談を受けています。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです

Posted by いとう茂 at
22:04
│Comments(0)
2021年06月10日
第2回ひきこもり講座のご報告②
ひきこもり講座のご報告①の続きです。
そしてひきこもり当事者の家族もしんどい。
本人だけではなく、家族の相談も受けていますが、
家族は話すことによって気づきがあることもあります。
当事者との話では、
第3者が1歩引いたところで聞くことで、
こういうことが好き、こういうことがしたいなど、
一緒に気づきを探せるようにと思っています。
相談窓口は怖いところではありません。
いろいろな相談員がいます。
いろいろな相談窓口があります。
相談員の話し方がキツイと感じた時は、
勇気を出して言ってもらえれば、
相談員の気づき、成長につながります。
「そんな話し方されたら、腹が立つわ!」など、
遠慮せずに相談員に言ってもらいたいです。
そして相談を聞くだけではなく、
ボランティア体験などにも一緒に行っています。
ひきこもっている本人は、
「誰にも必要とされていない。」と
心を閉ざしています。
ボランティアの良いところは、
小さなことでも「ありがとう。」と言ってもらえる。
「手伝ってくれてありがとう。」と言ってもらえる。
ひきこもっている本人は、「ありがとう。」と
言ってもらえる体験をすることがありません。
私自身(八田さんのことです!)、
職場の中で「ありがとう。」と言われることが多く、
気持ちがいいです。
自分もたくさん「ありがとう。」と言いたくなります。
「ありがとう。」と言ってもらえると、
「もう少しがんばろうかな。」と思ったりもします。
これは夫婦関係でも、親子関係でも同じだと思います。
「ありがとう。」の一言で段々変わってくると思います。
そしてひきこもりの心理ですが、
生まれてこの方、ひきこもっています、
という人はいないと思います。
人生歩いていたら、いつの間にか
出口のないトンネルに差し掛かっていた。
周りまっくら。誰もいない。
働きたくてもしんどく、他人との関わりがなくなる。
外に出られなくなり、出れないのは何で?と
自問自答、葛藤から、
自己存在意義の危機が訪れる。
何をやっても何も感じなくなる。
自分を認められなくなる。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです
そしてひきこもり当事者の家族もしんどい。
本人だけではなく、家族の相談も受けていますが、
家族は話すことによって気づきがあることもあります。
当事者との話では、
第3者が1歩引いたところで聞くことで、
こういうことが好き、こういうことがしたいなど、
一緒に気づきを探せるようにと思っています。
相談窓口は怖いところではありません。
いろいろな相談員がいます。
いろいろな相談窓口があります。
相談員の話し方がキツイと感じた時は、
勇気を出して言ってもらえれば、
相談員の気づき、成長につながります。
「そんな話し方されたら、腹が立つわ!」など、
遠慮せずに相談員に言ってもらいたいです。
そして相談を聞くだけではなく、
ボランティア体験などにも一緒に行っています。
ひきこもっている本人は、
「誰にも必要とされていない。」と
心を閉ざしています。
ボランティアの良いところは、
小さなことでも「ありがとう。」と言ってもらえる。
「手伝ってくれてありがとう。」と言ってもらえる。
ひきこもっている本人は、「ありがとう。」と
言ってもらえる体験をすることがありません。
私自身(八田さんのことです!)、
職場の中で「ありがとう。」と言われることが多く、
気持ちがいいです。
自分もたくさん「ありがとう。」と言いたくなります。
「ありがとう。」と言ってもらえると、
「もう少しがんばろうかな。」と思ったりもします。
これは夫婦関係でも、親子関係でも同じだと思います。
「ありがとう。」の一言で段々変わってくると思います。
そしてひきこもりの心理ですが、
生まれてこの方、ひきこもっています、
という人はいないと思います。
人生歩いていたら、いつの間にか
出口のないトンネルに差し掛かっていた。
周りまっくら。誰もいない。
働きたくてもしんどく、他人との関わりがなくなる。
外に出られなくなり、出れないのは何で?と
自問自答、葛藤から、
自己存在意義の危機が訪れる。
何をやっても何も感じなくなる。
自分を認められなくなる。
本日はここまでで、
続きは次回のブログです

Posted by いとう茂 at
22:46
│Comments(0)